 |
 |
| Vol.36 続々・一本の木[2008.2.29] |
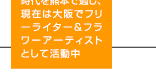 |
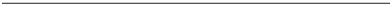 |

|
「自然」に対する思いは人それぞれでしょうが、概ね人は「美しく豊かな自然」に感動し、安らぎます。そして、自然の力や神秘を感じたとき、「偉大なる自然」に畏敬の念を抱くものです。
写真家・白川義員さんは、原始の風景や聖地の写真で有名な方ですが、人類の祖先である猿人が凄絶な恐れと感動を持ったであろう森羅万象を自分もこの目にしたいとの思いから、アルプスやヒマラヤなどの大自然に挑んだそうです。白川さんの説を借りると、猿人たちは自然とその背後の宇宙に遍満する偉大な精神の存在、偉大な霊性を感得し、その存在に畏敬の念を持ち、敬虔な祈りを捧げた、つまり信仰心を持った。それが原始的な宗教の成立であり、信仰心を持ったが故に彼らに精神革命が起った。つまり、猿人が人間になった理由がそこにある、といいます。
さらに白川さんは、アインシュタインがそうした人類の原初的感情を「宇宙の秩序と統一とに対する根本直感に基く畏敬の感情」と評しているといい、アインシュタインも相対性原理を発見する過程でその戦慄的な畏れを持ったのだろう、と推測しています。そういえば、DNA解明の世界的権威とされる筑波大学名誉教授・村上和雄さんは、見事な調和のもとで働く遺伝子について研究する中で、その調整を可能にしているものの存在を「サムシング・グレート(偉大なる何者か)」と呼ぶようになりました。
わずかこれだけの他者の言から結論めいたことを言うのは無謀で独善的ですが、なにやら、宗教と科学が、また、宇宙と生命が、同根から伸びた気宇壮大な大樹のように感じてきませんか。
で、それはさておき、その原初的畏怖の感情が、自然のすべてに神を観るアニミズムとして発展し、世界の民族の原点にあるわけですね。日本では樹をはじめ岩や花などを神が現れるとき乗り移るものと崇める依代(よりしろ)信仰となり、江戸時代まではおおらかな神仏習合でしたから、その名残はあちこちで目にすることができます。
自然信仰や精霊信仰を否定するキリスト教のヨーロッパでも、アニミズムの名残があるようです。というのも、キリスト教以前のヨーロッパの精神世界の主柱だったケルト文化には妖精伝説なども多く、泉やオークの樹に神が宿るとされていました。キリスト教はそうした信仰を排しながら広まったのですが、ヨーロッパの田舎では今も道の脇や洞窟の奥に、お地蔵さんみたいにマリア像が置かれているのを見かけるとか。
そして、なんと、フランスのアルヴィーユという村には内部にチャペルを持つオークの樹があり、チャペル1階にはマリア像、外2階にはキリスト像が祀られているそうです。この「木の中のチャペル」は、朝日新聞で連載中の「奇想遺産」で紹介されていたのですが、「清らかな泉や年月を経た巨木に聖なるものを感じる気持ち、それは大きく地母信仰といっていいと思うが、キリスト教布教以後もヨーロッパの田舎に残り、そうしたところに聖母を置いたのではないか」(建築史家・藤森照信さん)と評しています。
▼「木の中のチャペル」が見られる「オランダと西ヨーロッパの古木」の英語サイト
http://82.94.219.20/~jpa/english14.htm
最初の「The Chapel-Oak of Allouville-Bellefosse」がそれ。自動翻訳にかけると素っ頓狂な日本語になりますが、大体のことはわかる…かも。
それにしても、聖なる木の内部に入り込んで祈るヨーロッパと、聖なる木に注連縄で結界をつくって祈る日本と、やはり民族の違いのようなものを感じますね。
 |
本コラムVol.30 <一本の木>でご紹介した、私にとってのなじみの一本の木ですが、「渡辺綱・駒つなぎの樟」の突き出た大きな幹は3本ではなく4本でした(写真左)。いつも決まった方向から見ていたので気づかなかったのですが、裏手から見て発見。面目ないです。あっちこっちから見なけりゃほんとの姿はわからないことってあるのですよね。
そして、もう一つのなじみの「楠木大神の楠」は、前回は道との関係をお知らせしたかったので遠景でしたが、今回は逆の方向からの近景です。ね、祠(ほこら)と鳥居がちゃんとあるでしょう(写真右)。鳥居が白いのは、ここに棲みついていたという巳さん(蛇)は白蛇ってことなのでしょうか。よくわかりませんが。
|
|
|
| |
 |
| |
 |
|